組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応WGによる人事部門へのヒアリング
<特別編 第6回>
| « 第15回 日本電気株式会社(前記事へのリンク) | 【特別編 第7回】安藤慶明氏へのインタビュー(次記事へのリンク) » |
北海道大学 吉原教授に聞く「博士のキャリア」に関するインタビュー
北海道大学 大学院教育推進機構 先端人材育成センター 教授 (副機構長、先端人材育成センター長、博士人材育成部長)。博士(工学)(大阪大学)。
北海道大学卒業後、1990年にNEC入社。半導体プロセスの研究開発、NECグループ全体の知的財産の調査分析および戦略立案・実行に携わった。2015年から北海道大学で教鞭を取る。また、北海道大学、東北大学、名古屋大学、筑波大学、横浜国立大学、お茶の水女子大学、新潟大学、立命館大学、大阪大学、神戸大学、兵庫県立大学、沖縄科学技術大学院大学の12大学で構成される「博士人材育成コンソーシアム」 のコーディネーターでもある。
●北海道大学 先端人材育成センター
https://fohred.synfoster.hokudai.ac.jp/
●博士人材育成コンソーシアム
https://ccdp.synfoster.hokudai.ac.jp/
●はじめに
本連載、「日本の人事と内部不正」では、これまで、組織で働く人間の満足(ES: Employee Satisfaction)向上のために、「働く環境を提供する側」がどのような工夫をしているかの取り組みについてヒアリングしてきた。今回は、視点を180度変えて、「働く側」に焦点をあて、そのマインドセットの涵養という観点から、北海道大学で「博士のキャリア」に関する様々な施策を展開している吉原拓也先生にお話をお聞きした。世界では高度な専門性を有する博士人材は、社会の様々な領域で活躍する状況が当たり前になっている。一方、日本では、職場側、働く側の双方に課題があり、必ずしもそうはなっていない。高度人材の労働市場が国際化している昨今、このことは、日本の国力を削ぐ要因の一つになっているものと考える。読者の皆さんには、今回の「博士のキャリア」に関するお話を契機として、働く側のマインドセット、そしてそれの社会的バックグラウンドについて考えて頂きたい。今回の特別編の趣旨はそこにある。

吉原先生は、北海道大学(大学院修士課程)を卒業後、NECで半導体の研究や知的財産の調査分析に携わり、在籍時に「博士(工学)大阪大学」 も取得。2015年から母校の北海道大学で教鞭を取り、現在は教授となっている。
また、北海道大学内の先端人材育成センターのセンター長として、博士のキャリアについての活動を大学の 枠を超えて行っている。現在、学校教育の頂点のひとつのはずの博士号の所持者が、企業などで活躍しきれていないという社会的な課題がある。この先端人材育成センターは、博士のキャリアに関する課題解決を目指している組織だ。以下にその現状や取り組みを紹介する。
●先端人材育成センターは、なぜ「博士のキャリア」を対象にしているのか?
北海道大学は、他の大学と同様に博士だけでなく、修士や学士の取得を目指す学生も多く在籍する国内有数の総合大学である。学生のほとんどは、他大学と同様に学部4年間の課程(学士)で大学生活を終える。その後、その一部が修士課程に進み、さらに 一部が博士課程に進むことになる。つまり、北海道大学も他の大学と同様に、博士課程の学生の占める割合はそれほど多くないと言える。
ではなぜ、ごく一部の博士課程の学生を対象とした先端人材育成を北海道大学が行っているのだろうか。その答えは、北海道大学が自らを「研究大学」と位置づけていることにあるという。大学の4年間は、ゼミや研究室に所属して卒業論文などを書くものの、一般的には「学術研究」と言われるレベルには達しない。
そして、次のステップの修士となっても、研究という世界ではまだまだ初歩レベルということらしい。そして、博士課程になってはじめて本格的に研究に携わることになる。特に、博士号を得るために欠かせない「学術雑誌への研究論文投稿の際の査読プロセス」が重要だという。大学教授等の専門家からなる複数の論文査読者から研究の内容に関する質問を受け、それに応える形で、論文のブラッシュアップをするが、それでも水準をクリアできない場合、その投稿論文は容赦なく学術雑誌への掲載が拒絶される。
研究論文は、この過程を繰り返すことで、初めて学術雑誌に掲載されることになる。多くの大学では、この学術雑誌 に掲載される研究論文がないと博士の学位を得ることはできない。吉原先生によると、この査読を受けるというプロセスこそが重要であり、その過程で研究において何が重要かという点が理解できるという。
この第三者による査読によって、研究という非常に高度なことを実行できるようになった先端人材だけが博士となれる。そして、現在の高度かつ複雑化する社会において、このような専門性の高い知識を所持し、研究ができる人材が一定以上いることが非常に重要なことなのだという。

北海道大学の先端人材育成センターは、2022年度からその体制がより強化されたという。具体的には、従来よりも 「学部から博士課程まで一貫したキャリア教育・キャリア支援を実施する体制」「個性を重視した博士人材の支援」の強化を行うことで、博士の質をさらに高めることを考えているようだ。つまり、北海道大学は博士という専門性の高い先端人材の育成 に本気で注力している。
●マスコミやネットが煽る「ポスドク問題」
高度な研究ができる博士という人材は、世間から誤解を受けやすい性格を持つという。特に、マスコミやネットの記事、コメント、掲示板などでは博士についての非常に偏った記載・投稿が注目を集める。これは、ネットやSNSなどでよく言われる「バズる」と言われる状況だ。
そのような例は枚挙にいとまがない。ネガティブな例 を取り上げて、それがあたかも博士のすべてのような扱いをすることが少なくない。しかも、ネットの世界では、そのような否定的で極端な意見がもてはやされる傾向が強い。一方、中立的な立場でのまっとうな意見は、ほとんどの場合で興味を持たれず「バズる」ことはない。
そのため、事実と異なる偏った見方の意見が是正されることは非常に少ない。それによって、博士は、多くの時間や努力 を重ねたにも関わらず、ネットの世界において、社会の役に立っていない存在だという否定的な世論が形成されてしまった。
本来であれば高度な知識を持つ専門的な人材であるはずが、その存在自体が社会問題であるかのように、「ポスドク問題(博士課程を修了した人のキャリアに関する問題)」と揶揄されるようになってしまった。そして、博士を目指す博士課程の学生自身も、その世論を必要以上に深刻に受け止めてしまっている。その結果、博士号を持つ自分自身を自虐的に語るような状況にもなっているという。
このような問題が起こるのは、博士という存在が非常に少数であることが少なからず要因となっている。例えば、現状の日本の大学生は、同じ年に生まれた同級生がおよそ120万人居るが、その年代で大学に進学する割合は、50%を少し超えるぐらいだ。それに対して、大学院(修士課程)への進学率は全体のわずか5%だという。
さらに博士課程に進むのは0.7%に過ぎない。しかも、この内訳の25〜35% には外国人留学生が含まれる。これを差し引いた結果、博士の割合は同年代の0.5%に過ぎない。しかも、その博士のいる場所は、大学や研究所など、非常に偏っている。そのため、一般の方が日常的に博士と交流を持つ機会は非常に少ない。つまり、誤解の解消がなされる機会そのものが少ないのだ。そのため、現在の博士に対するマイナスのイメージが払しょくされるには、まだ多くの時間がかかるだろう。
●現在の「博士のキャリア」とは?
このような博士への誤解は、博士のキャリアそのものへの誤解だと言える。その誤解を解くためには、博士のキャリアについてもう少し深堀りする必要がある。これまでの博士のキャリアとは、その多くが研究所と大学のどちらかだった。博士は研究をする専門家なので、このような研究機関に在籍しているのは当然であり、このことに以外な感じを持つ方は多くは無いだろう。
しかし、意外にも現在の博士は、最初からそのようなキャリアを目指していない場合も少なくないという。例えば、研究者以外で博士が目指すものの代表はコンサルタントだ。コンサルタントは、非常に高い専門性を要求され、給与水準も高いことが多い。そのような意味で、博士はコンサルタントにマッチしやすい職業だと言える。
また、この他にも特別な専門知識を活用した仕事で博士が活躍するシーンは少しずつ多くなっているらしい。世界では政府の要職に就く博士所持者が多くいる。それに対して、日本では、有識者としての大学教授などを除き、そのような存在はほとんど居ないことから、カウンターパートのバランスの問題となる。世の中は、以前よりも確実に高度化、複雑化している。このような世の中において、博士の持つ専門性が重要性を増していくのは間違いないだろう。
それでも、「博士のキャリア」は、一般的な企業では、まだまだ誤解され続けていることが少なくない。その誤解による失敗例は次のようなものだ。昨今の人材難もあって、多様な人材を活かす戦略としてダイバーシティを推進する企業がある。その企業が(人材採用を多様化させようと)博士を採用するが、博士のためのキャリアパスを準備できていない場合がある 。そして、その人材を他の新入社員と同様に従来通りのルーチンワークをさせてしまう。さらに、自社の社風に染まることも要求してしまう…。
これの何が問題かというと、多くの時間と努力を費やして得た博士の専門性を無視していることだ。結局、「多様性を重視する」という掛け声だけは大きくても、受け入れ側が博士の専門的な知識を活かすための準備がまるで出来ていない。高度な専門性を持つ人材の強みを活かすという博士採用の前提条件が崩壊しており、せっかくの専門性を捨てさせることに繋がるのだ。このようなミスマッチの結果として、企業は「博士は専門にこだわるので使えない」と思い込み、博士は「自分は役に立たない」と思い込むという。これは、双方にとって不幸な状況だ。
そして、このようなミスマッチが是正されない要因は、採用する企業側だけでなく、博士(および博士課程の学生)の側にもあるという。それは、博士号を取得しても本人自身の自己肯定感が低いことだ。結局、博士課程の在籍者といってもその身分は学生に過ぎない。社会の中で卒業後の地位を保証されている訳では無く、学生であった期間が長いために社会での経験も少ない。その結果、本人が先述の「ポスドク問題」を真に受けてしまうことが少なくないという。
このような経緯や、博士向けの就活情報サイトが少ないこともあって、 自己肯定感の低い博士課程の学生の就職活動は、企業に提出するエントリーシートも、一般的な(四年制)大学卒業予定の学生と同じようなテンプレ的なものになってしまうことが少なくないそうだ。そうなると、採用側も一般の就活生と同じ土俵で比較しまうようになってしまう。その結果、年齢層が高い分だけ不利になるという「ポスドク問題」のシナリオ通りになってしまう。
博士であるということは、人と異なる高い専門性を持っているという点が最大の強みとなる。そのため、博士課程の実績を活かすのであれば、学生は「自分の持つ専門性こそが高度化・複雑化する社会や企業の価値になる」という説明をしなければならない。
●博士を受け入れられない日本社会の課題
従来よりも、社会が確実に高度化・複雑化しているという点については、多少の考え方の違いはあるとしても、総論としてこのことに異を唱える方は少数派だろう。さらに、そのような社会においては、企業も従来の延長線上で物事を考えていては、激しい競争を勝ち抜くことは難しい。複雑な社会だからこそイノベーションを起こす必要がある。そして、そこにこそ専門性を高めた博士の存在意義がある。
しかしながら、現在、社会においてこのことが合意形成されているとは言えない。この点が、日本の社会における博士の活用のための最大のハードルだと言える。そして、このハードルを越えるためには、博士を送り出す大学側と受け取る社会の双方に課題がある。
まず、博士を受け取る企業や組織側について言及しよう。日本の多く の企業は、博士を採用したことが無いか、あってもそれはごく少数だと思われる。それらの企業は、博士が専門性を持った人材だという事をまず何よりも認識すべきだ。彼らの持つその専門性を活かすことができれば、それはイノベーションのための引き金となる。つまり、イノベーションを起こしたいのであれば、博士の専門性を活用できるような組織や体制を整備するべきなのだ。
これだけを耳にすると、博士を活躍させるために周りが変わらなければならないという、一方的な偏った意見に聞こえるかも知れない。しかし、たとえ博士といえども、自分を活かす環境を自分で築き上げ、さらに活躍するのは困難であることから、結果としてそういう話にならざるを得ないのだ。
世界はすでに専門的な知識を活用することで成り立っている。日本がこれからも世界のトップクラスの経済力を持ち続けるためには、このような専門性が必要になることは明らかだ。そして、日本以外の諸外国では、欧米などの先進国のみならず、発展途上国でさえもこれが常識だということだ。現在、日本への留学生は、中国や韓国、その他のアジア圏などからが圧倒的に多い。これらの国からの留学生がこのような疑問を口にすると言う。その疑問とは「なぜ、日本人の優秀な(修士課程の)大学院生は、博士課程に進まないのか?」というものだ。
すでに世界においては、博士という存在は、大学や研究機関のみならず、多くの企業や組織において重要な戦力となっている。そして、彼らのような留学生たちも母国に帰れば、当然そのような存在になる。そのため、日本の優秀な学生が博士課程に進まないことに疑問を感じるのだという。つまり、「ポスドク問題」などという社会問題が 大きく取り沙汰されるのは、日本だけなのだ。
技術の進歩によって、この世の中は現在以上に社会全体で高度な専門性が必要とされることは確実だろう。そして、将来における日本の競争力の維持や向上には、専門性を持つ人材が不可欠だと言える。そのような人材とは、かなり高い確率で博士号を持つような人々になるはずだ。このような先端人材の有効活用が、このグローバル経済の激しい競争に勝つための重要な要素になる。この重要なピースがきちんとはまるかどうかが、日本社会が今後発展を続けられるかどうかの試金石になるといえる。
さらに、課題は博士を受け取る社会だけではなく、送り出す大学 側にもあるという。たとえば、自分が研究している内容について専門的な言葉では語れるものの、一般の人々にわかるようには説明できない学生が散見される点だ。博士課程の3年という限られた期間で、一つの研究成果を取りまとめるためには、その研究に没頭するのもやむを得ないことなのかもしれない。しかし、その研究の社会的な背景や、研究成果が社会にどう役立つかをわからないまま研究していると、折角獲得した専門性を社会で活かすことが困難になってしまう。
アカデミックな世界でのメリットや先進性ばかりを追求するのも良いとは言えない。いくら高尚な理想を述べても、自己満足的なものとなりがちだからだ。アカデミックの世界の高尚な理想は、時に免罪符のようにもなっているという。世の中から有用な研究だと認識されるには、研究テーマの内容の何割かには、近い将来、社会や企業などへ何らかの形で還元できること含まれるべきであろう。
そして、そのことを博士課程の学生に伝えなければならない大学の先生側にも課題があるという。多忙なため、学生と接する時間が限られていることもあるが、学生の指導が研究そのものに偏ってしまい、研究の本質や社会とのつながりにまでその指導が及んでいない教員も少なからず存在する。
その場合は、学生の側から議論を仕掛けて、研究の全体像や本質を引き出す必要があるのだが、そのすべてを学生に要求するのも酷な話だ。もちろん、解決のためのフォローはされているものの、ケースが無数にあることや人間同士の相性的な問題も絡むことから、すべてがクリアされることも無いという。
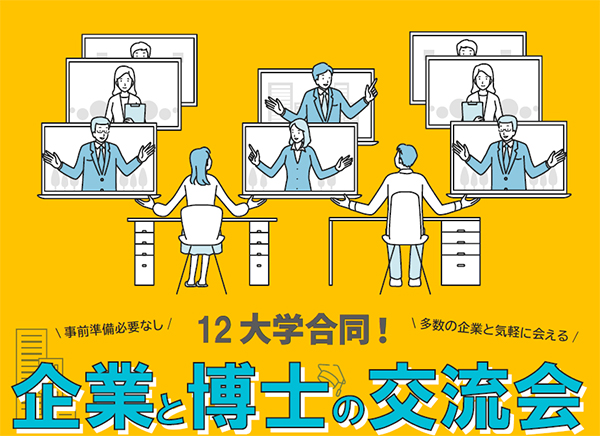
このように、「博士のキャリア」というものを社会的に合意形成していくためには、博士の送り出し側と受け取り側の双方にまだまだ課題が残っているようだ。このような誤解や課題が少しでも減らせるように、北海道大学の先端人材育成センターでは「学生と企業の交流の場」を作ることを積極的に推進しているという。
さらに、この取り組みは北海道大学だけのものではない。吉原先生がコーディネーターを務める「博士人材育成コンソーシアム 」は全国の12もの大学が連携することで、さらに大きなムーブメントへ発展させようとしている。このような活動によって、社会が博士の効果的な活用法に気づき、それが海外と同様に定着することになれば、日本社会が「博士のキャリア」を積極的に活用するようになる。吉原先生は、そう信じて日々の活動を推進しているのだ。
●おわりに
本インタビュー連載では、これまで、働く側の満足度向上のために、「働く環境を提供する側」がどのような工夫をしているかの取り組みについてヒアリングし、紹介してきた。一方、「働く人間が働く満足を得ながら働き続ける」ためには、「労働環境を提供する側」のみの視点では不十分であり、「働く側」のマインドセッティングなどの視点も欠かせない。
今回は、通常行っている「労働環境を提供する側」の視点からではなく、逆の「労働環境の受益者」である「働く人間」を育てる立場から、その「マインドセッティング」や「キャリアについての考え方」などに関して、「どのような考え方で、どう涵養しようとしているか」のお話を、博士人材のキャリア教育に関わられている北海道大学の吉原先生に伺った。
「労働環境」の「提供側」と「受益側」の波長があってはじめて本当の「働く人間の満足」が実現できるのではと考えてのことである。その観点から、博士人材という「高いレベルの働き手」のキャリアを考え、産業界に送り出す立ち位置にいる吉原先生のお考えや、教育上における工夫は、「働く人間が働く満足を得ながら働き続ける」ための示唆になりうるはずだ。
私たちはすべて働く側の人間である。これを忘れてはいけない。これまでのヒアリングとすこし切り口が異なるが、「労働環境を提供する側」にとっても今までにない視点からの、興味の持てるお話だったのではないだろうか。
| « 第15回 日本電気株式会社(前記事へのリンク) | 【特別編 第7回】安藤慶明氏へのインタビュー(次記事へのリンク) » |