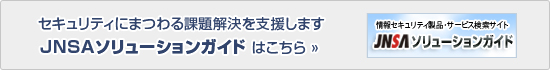HOME�@���@ ���J�����E�������T���̕��@���@JNSA �Z�L�����e�B�\��j���[�X
JNSA 2025�Z�L�����e�B�\��j���[�X �`�U��h�R�A�f�W�^���Љ�ɐM���\���̒n�k�ϓ��͐��邩�`
�Z�L�����e�B�\��j���[�X�I�l�ψ���ψ����@��� �ē�Y
2025�N�̑�1�ʂ́A�����̓ǎ҂̗\�z�ǂ���A����ЊQ���Ə̂���郉���T���U���ɂ���Q�Ɖe���̊g��ł���B���̑�\�i���A�T�q�O���[�v�z�[���f�B���O�X��A�X�N���̔�Q���B�����T���U���ɂ���Q��Ƃ̋Ɩ�����~���邱�Ƃ��A�֘A���鑽���̊�Ƃ₻�̐�̎s���ɑ���ȉe���������炷���ƂɂȂ����B�r�[���̏o�ׂ��~�܂�Ε�M�t�g���i�ɂ��傫�ȉe�����\�ꂽ�݂̂Ȃ炸�A�Ⴆ�A�X�N���̕����@�\�̒�~�ɂ���Ê֘A���ނ̔z������ȂǁA�����̋Ǝ�ɉe�����y�ёΉ��ɔ���ꂽ�̂ł���B
�gIT�V�X�e���u2025�N�̊R�v�̍�����DX�̖{�i�I�ȓW�J�h�ƕ����t����DX���|�[�g������30�N�Ɍo�ώY�ƏȂ���o����Ĉȍ~�A�����̊�Ƃ�DX�i�f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����j�Ɏ��g��ł������A�\���Ȑ��ʂɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ�����������ʓI�ł���B�������A�T�C�o�[�U�����s�������ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��w�i�ɂ͒�����DX���Z�����Ă��鑤�ʂ����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�T�C�o�[�U���ł͐l�͎��ȂȂ��Ȃǂƍ��������Ă�������܂ł̌����͉��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��̂ɖ�����K�v������B
���N�̏\��j���[�X�ɂ́A�����T���U���ɉ����ď،������������IIJ�s���A�N�Z�X�AETC��Q�Ȃǔ�Q�j���[�X��4���A�T�v���C�`�F�[�������Ɍ������]�����x��\���I�T�C�o�[�h��A�Z�L�����e�B���x�����O���x�A�ϗʎq�v�Z�@�Í��Ȃǂ̐V���Ȏ��g�݃j���[�X��4���Ɲh�R���Ă���A����2���͎��ƍU�߂̗��ʐ�������AI��FeliCa�̐Ǝ㐫�̌��\�ɌW��j���[�X�ł���B
��Q�j���[�X�ƐV���Ȏ��g�݃j���[�X�̐����h�R���Ă������Ƃɂ͑傫�ȈӖ�������ƍl�������B��X�̎Љ���x����M���̍\�}�́A����܂ł̗��j�ł��Z�p�̔��B�ɉ����đ傫���ω����Ă����B����̔��B���玆�����Z�p�̊m���Ȃǂ��o�ăf�W�^���Z�p�̎���ɂȂ�A�V���ȋZ�p��p���Ă���ɐM���̍\�������łȂ��̂ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Z�L�����e�B�j���[�X�͂��̂悤�ȕω��̕\�ʂ�`���Ă���Ƃ���A�f�W�^���Z�p�ɂ��M���̊m���͍��コ��Ɋ����̎d�g�݂̔j��ȂǂƂƂ��ɐV���Ȏd�g�݂̍\�z�E���y�Ȃǖ{�i�I�Ȓn�k�ϓ����N���Ă���ɈႢ�Ȃ��B���̐�삯�����N�̃j���[�X�ł��邱�Ƃ��F�肽�����̂ł���B
X2025�Z�L�����e�B�\��j���[�X
�y��P�ʁz 9��29���@��������Ƃւ̃T�C�o�[�U���A���܂�g�ЊQ���h�Ǝw�E����鋺��
�y��Q�ʁz 11��28���@�T�v���C�`�F�[���ɔg�y����T�C�o�[��Q�A�������ɔ��W����P�[�X��
�y��R�ʁz 4��3���@���Z���A�،������������Q�}���Œ��ӊ��N�A�ēw�j������
�y��S�ʁz 2��27���@�����`�h���p���s���A�N�Z�X�̒������R�l�ߕ߁A12���ɂ�
�y��T�ʁz 5��16���@�u�\���I�T�C�o�[�h��v�֘A�@�Ă������A���ƃT�C�o�[�������̐ݒu��
�y��U�ʁz 3��25���@IoT���i�ɑ���Z�L�����e�B���x�����O���x�iJC-STAR�j�̉^�p���J�n
�y��V�ʁz 4��16���@IIJ�s���A�N�Z�X�A���{������O���[�v��n��ȂNJe���ɉe��
�y��W�ʁz 4��6���@���������⒆�����Ȃǂ�ETC��Q�@7�s���A�ꕔ���[����
�y��X�ʁz 8��28���@FeliCa�̃Z�L�����e�B�Ǝ㐫�ŗ��p�҂ɕs���L����
�y��P�O�ʁz 11��20���@���{���j�A2035�N�܂łɑϗʎq�v�Z�@�Í��iPQC�j�Ɉڍs
�y�ԊO�ҁz 11��18���@2025�N11��18���̓C���^�[�l�b�g����ꂽ��
��2025�Z�L�����e�B�\��j���[�X���I��ψ��E���
�ψ����E��؞ē�Y�^�D�Ώ��V�^�_�R���N�^����E��^�����W��^���R�@�o�^
�������m�^���Y�@���^�|���a�O�^�����G��^���{�@�ׁ^�ێR�i�Y�^���c�[�i
�y��P�ʁz 9��29���@��������Ƃւ̃T�C�o�[�U���A���܂�g�ЊQ���h�Ǝw�E����鋺��
�`�A�T�qGHD�A�A�X�N�����̃����T����Q�A�e���͎s���ɂ��`
2025�N9��29���A�A�T�q�O���[�v�z�[���f�B���O�X�i�A�T�qGHD�j�́A�����T���E�F�A�ɂ��T�C�o�[�U�����A��K�͂��V�X�e����Q�����������Ɣ��\�����B���̉e���ŁA�E�o�׃V�X�e���╨���֘A�̋@�\����~���A�S���̍H��E�̔�����ŋƖ��ɑ傫�ȍ����������B���i�̋����ɂ��x�ꂪ�o���B�e���̓A�T�qGHD�ɗ��܂炸�A�A�T�q�̏��i�s����₤�ׂ��A�}�ȑ��Y�𔗂�ꂽ���Ƒ��Ђ��N������ɂ������𗈂����B����ɒ����̌��ʁA��191�����ɂ̂ڂ�ڋq��]�ƈ������l����o�����\�������\����A�l���ی�̊ϓ_�ł��d��ȃ��X�N�����炩�ɂȂ��Ă���B
�A�T�qGHD�̎��Ă��Ȃ��Ȃ������Ɍ�����Ȃ����A10��19���ɂ́A�����E�ʔ̑��̃A�X�N���ł������T���E�F�A�ɂ��T�C�o�[�U���ɂ��A���Ђ̃T�[�r�X���V�X�e����Q���������A�I�����C���ɂ�钍����t��o�Ɩ����ꎞ��~�B��ƁE�l���Ǝ�ւ̋������啝�ɑ����B���̔�Q�́A�A�X�N���̕����T�[�r�X�𗘗p���鏬���E�����Ԃɂ��g�y���A����Ǖi�iMUJI)�A���t�g�iLOFT�j�ȂǑ��Ђɂ��e�����y�ڂ��Ƌ��ɁA��Ê֘A���ނ̔z�����x������Ƃ������Ԃɂ܂Ŕ��W�����B�܂��A���̎��Ăł��A�l����_�[�N�E�F�u�Ɍ��J����Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B
�����2���̃C���V�f���g�́A�P�Ƃ̊�Ƃ����łȂ��T�v���C�`�F�[���S�̂Ђ��Ă͋ƊE�S�́A�Љ�S�̂ւ̉e��������ɂ��Ă���B���Ƃ̃V�X�e���_�E�����S�����x���ŏ��i�����╨���ԑS�̂Ɏx��𗈂����ق��A�c��Ȍl��o�̃��X�N�����������A��ƐM�p�ɐ[���ȉe����^���Ă���B����͋ߔN�̑䕗��n�k�ȂǂɋN������H��̔�Ђ╨���Ԃ̔�Ђɂ��e���Ǝ��Ă���A�T�C�o�[�U�����ЊQ���̔�Q�������炵���邱�Ƃ��A���炽�߂ĔF�����ꂽ�Ƃ����悤�B��Ƃ��O���Ɉˑ�����IT�E�����l�b�g���[�N�̃Z�L�����e�B�Ǝ㐫�́A�r�W�l�X���f�̃��X�N�傳���Ă���A�C���V�f���g�Ή��v��̍����Ј��ւ̋���A�ŐV�̖h��Z�p�����̕K�v�������������яオ���Ă���B
�y��Q�ʁz 11��28���@�T�v���C�`�F�[���ɔg�y����T�C�o�[��Q�A�������ɔ��W����P�[�X��
�`��Q�̘A���A������肩��l����ϑ���Ǘ��̏d�v���ƕ]�����x�̈Ӌ`�`
��1�ʂƂȂ����A�A�T�qGHD�ƃA�X�N���̗��Ђւ̃����T���E�F�A���Ắu��Q�͓����҂ɂƂǂ܂�Ȃ��v�Ƃ��������������F�������鎖��ł������B�T�C�o�[�U���͎�����ϑ����ȂǑ����̊W�҂ɘA�����A�����Ȃ��Ƃ���Ŋm���ɑ������g�傳���Ă����B
2025�N�́A11��28���̓��{�o�ϐV���̕��Ŏ����ꂽ�Ƃ���A����������Q�̘A�����u�����v�Ƃ����`�Ō��݉������N�ł������ƌ�����B�O���s��NTT�����{��9,500���~�̘a���A�G���P�C�V�X�e��������3���~�̏W�c�i���A���}�����E������ÃZ���^�[�ɂ�����10���~�̘a���A�������f�B�A�ŕ�ꂽ�֒ʂɂ��ϑ����ւ�10���~�̔������S�\�\�B��������A�ߋ��̃T�C�o�[�U�����A���Ԃ��o�Ċ�ƊԂ̖@�I�ӔC�Ƃ��ĕ��o��������ł���B�����ɉ����邩�^�������A���̌��_�������ꂽ�_�͋����[�����A�T�C�o�[��Q���������ւƔ��W�����邱�Ƃ͗h�邬�Ȃ������ł���B
�{���A�ӔC�̏��݂́A�_���̋`���┅���z�̐����Ƃ������g�g�݂ɂ���Đ�������Ă����B�����X�̌_������������Ƃ͕s�������A���E������̂������ł���B�@�I���萫���m�ۂ��邽�߁A���炩�̐��x�v���������ׂ��i�K�Ɏ������͍����������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
����������Q�̘A���┅������w�i�ɁA�ϑ���Ǘ��̏d�v���͈�i�ƍ��܂��Ă���B�o�ώY�ƏȂ�4��14���Ɍ��\�����u�T�v���C�`�F�[�������Ɍ������Z�L�����e�B���]�����x�v�̒��Ԏ��܂Ƃ��́A�ϑ���Ǘ����ɂ������̑O�i�ł���B��Ƃ��ƂɈقȂ�`�F�b�N���X�g�ɖ|�M����Ă����ϑ���A���ɒ�����ƂɂƂ��ċ��ʂ̕]�������������Ӌ`�͑傫���B
�T�C�o�[�U���͂P�Ђ����̖��ł͂Ȃ��B�T�v���C�`�F�[���ɘA�Ȃ邷�ׂĂ̊�Ƃ��A���X�N�����L���铖���҂Ƃ��Č��������A�x�������Ȃ���S�̂̋��Ր������߂Ă����\�\���̊o�傪���ꂩ��̎Љ�ƎY�Ƃ�����ՂƂȂ�͂��ł���B
�y��R�ʁz4��3���@���Z���A�،������������Q�}���Œ��ӊ��N�A�ēw�j������
�`�f�W�^������̏،��ƍ߂�20�N�z���́g�F�h���`
�،������������Q���A11���܂ł̗v���s�������7100���~���ɒB���A�[���ȎЉ����ƂȂ��Ă���B
���̎���͌ÓT�I�ȏ،��ƍ߂ł���A����̊��̔���������A���ŏo���Ӑ}�I�Ɋ�������グ���i�o���v�j��A�ʂ̌����ō��l�Ŕ��蔲���ė��v��i�_���v�j�Ƃ�����@���A�l�b�g�o�R�ő��l�̏،�������������i�n�b�N�j�g������Ȃ��悤�Ɏ��s���邱�Ƃ���u�n�b�N�A�p���v�E�A���h�E�_���v�v�ƌĂ�Ă���B
���{�����́A�،���Ђ����t�B�b�V���O���\��A���ގ�ɓ��������C���t�H�X�e�B�[���[�i�}���E�F�A�j�ɂ���āAID�ƃp�X���[�h�����܂�邱�Ƃɂ���B��s�ł�2010�N������t�B�b�V���O���\���ɂ����������肪�����������Ƃ���AMFA�i���v�f�F�j�̓������i��ł������A�،��ƊE��MFA�̓������i��ł��炸����W�I�ɂȂ����B
�܂��A��s�ƊE�ł�2005�N���́u�U���L���b�V���J�[�h���v���_�@�ɗa���ҕی�@���������A�T�C�o�[�ƍ߂ɂ������Q�ҕ⏞���s���Ă��邪�A�،���Ђ͓��@�̑ΏۊO�ł��邽�ߕ⏞�̖@�I�����������A��Q���g�傷��܂őx�ꂽ�\�����w�E����Ă���B
���̎��Ԃ��A���Z���Ɠ��{�،��Ƌ����10�����ēw�j������K�C�h���C����������MFA��K�{�Ƃ����B�܂��A�a���҂ɑ���⏞�͌Ђ̔��f�Ŏ��{����Ă���B
������MFA�Ƃ����Ă����[����SMS��p���������^�C���p�X���[�h�́A���A���^�C���t�B�b�V���O�ɑ��Ă͑ϐ����Ⴍ�A���ϐ��̍���FIDO2/�p�X�L�[�F�̓�����A����ɂ͉��B��eIDAS 2.0�̂悤�ȃg���X�g�T�[�r�X�̌������K�v�ł���B���̏،�������������́A�،��ƊE�����łȂ��A����̃C���^�[�l�b�g��̃T�[�r�X�Z�L�����e�B�S�̂ɂƂ��đ�ȋ��P�ł���B
�y��S�ʁz 2��27���@�����`�h���p���s���A�N�Z�X�̒������R�l�ߕ߁A12���ɂ�
�`���|�I��AI�p���[�̌��Ɖe�@�U����AI�A�h���AI�`
AI�Z�p�������I�ɐi�����Ă���A���܂��܂ȕ���ő傫�Ȑ��ʂ������Ă���B���������̃p���[�́A���̌��ʂ����łȂ����̌��ʂ����݂����Ă���B2���A���삵���v���O�����Ōg�ѓd�b��Б��́u�y�V���o�C���v�ɃA�N�Z�X�����s���ȗ��v���Ƃ���������3�l���ߕ߂��ꂽ�B12���ɂ̓C���^�[�l�b�g�J�t�F���́u����CLUB�v�ɕs���A�N�Z�X���s�����Ƃ������Z�����ߕ�����A��������U���v���O�����̍쐬��AI�̏�������Ă����B��������`���b�gGPT�ō�Ƃ̌������⏈�����x�̌���V�X�e���̖h�������蔲������@�A�s���A�N�Z�X�����݂�Œ��ɃG���[���b�Z�[�W���o���ۂ̑Ή������₵�A�@�\�����P�����Ă����Ƃ����B
�ߔN�͒ʏ�̃v���O�����J���ł�AI�����p���鎎�݂��i�߂��Ă���A���ɏ��w�҂ɂ͌��ʂ����邱�Ƃ��킩���Ă���B����̎����͂��ꂪ�Z�L�����e�B�Ɉ��p���ꂽ�킯�ŁAAI�̐��������p���u���v�Ƃ���Ȃ�A����̂悤�Ȉ��p�́u�e�v�ƌ����邾�낤�B
�Z�L�����e�B�ɂ�����AI�̈��p�̓v���O�����J�������ɂƂǂ܂�Ȃ��B8���A���[���b�p�̃T�C�o�[�Z�L�����e�B���ESET�Ђ��AAI���g���V�����^�C�v�̍U���v���O�����������Ɣ��\�����B���̃v���O�����́A�N���E�h���AI�ɓK�X�₢���킹���s���Ȃ���^�[�Q�b�g�ƂȂ����R���s���[�^���̋@�����̍����t�@�C����T������Í���������Ƃ������s���ȍU���������s���BAI�����p���邱�Ƃɂ���āA���x�ȍU�����ʂɍs�����Ƃ��\�ƂȂ����B
����������ł́A�Z�L�����e�B�ɂ�����u���v�̊��p������ɂȂ��Ă���B�]������u�A�m�}���[���o�i�ُ팟�o�j�v�ƌĂԎ�@�ōU�������m���鎎�݂��Ȃ���Ă������A�����AI�ɂ�点�邱�Ƃɂ���āA�c��ȒʐM�̒����炳�܂��܂ȃT�C�o�[�U����ƍߍs�ׂ�v���Ɍ��o�ł���悤�ɂȂ�\��������B�܂��A���ׂ��V�X�e���ɑ��Ă��炩����AI�����p�����^���U�����s���A�Ǝ�i�������Ⴍ�j�ȉӏ����݂��������݂�����B
AI�����͂ȃp���[������悤�ɂȂ������݁A�Z�L�����e�B���AAI�𐳂����ړI�̂��߂Ɋ��p���邱�Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă����ƌ����邾�낤�B
�y��T�ʁz 5��16���@�u�\���I�T�C�o�[�h��v�֘A�@�Ă������A���ƃT�C�o�[�������̐ݒu��
�@ �`���Ď�v�����݂̃T�C�o�[�Z�L�����e�B���{���������ҁ`
���炭�c�_����Ă����u�\���I�T�C�o�[�h��v�֘A�@�Ăł����T�C�o�[�Ώ��\�͋����@�y�ѓ������@�����E���������B����ɂ��A�T�C�o�[�Z�L�����e�B�헪�{���̖{��������t������b�Ƃ��A�S�Ă̍�����b��{�����Ƃ���g�D�ɉ��g���ꂽ�B
�܂��A�������7���ɂ͓��t�T�C�o�[�Z�L�����e�B�Z���^�[�iNISC�j�W�I�ɉ��g���A�T�C�o�[���S�ۏᕪ��̐�����ꌳ�I�ɑ����������鍑�ƃT�C�o�[�������iNCO�j���ݒu���ꂽ�B
���̖@���ŋ�̓I�ɍs���銈���͍���c�_�̏�ŏڍׂ����߂��Ă������A�T�C�o�[���S�ۏᕪ��ł̑Ή��\�͂����Ď�v���Ɠ����ȏ�Ɍ��コ���邱�Ƃ�ڕW�ɂ����@���ł���A��ȃ|�C���g�͇@�����A�g�i�����@�j�A�A�ʐM���̗��p�i�����@�j�A�B�A�N�Z�X���Q���[�u�i�����@�j���B
���N�͓��ɁA�����T���U���ɂ���Q��Ƃ̋Ɩ�����~���邱�ƂŁA�V�X�e�������łȂ������̕������~�܂�A�����Ƃ����łȂ�����҂ł���l�ɂ܂ő���ȉe���������炷���������������B�܂��A���N�̎Q�c�@�I���ł͊O�����͂ɂ��I������̎w�E��A�C�O�̃n�b�J�[�ɂ�鍑�����[�J�[�ւ̃[���f�C�U���ȂǁA���͍U���ɂ͎���Ȃ����̂̈��S�ۏ��̌��O��������d��ȃT�C�o�[�U���Ȃǂ��������Ă���B
�Љ�C���t�����x�����Ƃ��ϋɓI��DX�𐄐i���A���֗��ʼn��K�Ȏs���������������ɂȂ��Ă�����Ԃ����߂ĔF�����邱�ƂƂȂ����Ƃ��ɁA���֗̕��ʼn��K�Ȋ�������ɔ��W�����Ă������߂ɂ́A�C�O����̋��Ђ��z�肵�Ȃ�����S�E���S�ȎЉ������Ă������Ƃ��K�v���낤�B
�u�\���I�T�C�o�[�h��v�֘A�@�Ăɂ͓K�ȉ^�c���Ȃ����̂��s��������ӌ�������悤�����A�@�����̎�|�ł���u����������o�ϊ����̊�Ձv�Ɓu���Ƌy�э����̈��S�v���T�C�o�[�U�������邽�߁A�\���I�ȃT�C�o�[�h������{����̐������邱�ƂŁADX���i�ɂ�邳��Ȃ�Љ�̔��W�Ɛ����ւ̉��b������ł��邽�߂̓y��ƂȂ��ė~�����Ǝv���B
���Q�l�F���t���[�@�T�C�o�[���S�ۏ�Ɋւ����g�i�\���I�T�C�o�[�h��̎����Ɍ����������Ȃǁj
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html
�y��U�ʁz3��25���@IoT���i�ɑ���Z�L�����e�B���x�����O���x�iJC-STAR�j�̉^�p���J�n
�`�K�ȃZ�L�����e�B��������IoT���i�̕��y�Ɋ��ҁ`
3��25���A�o�ώY�ƏȂ��A�uIoT���i�ɑ���Z�L�����e�B���x�����O���x�iJC-STAR�j�̉^�p���J�n�v�Ƃ����\���Ȃ��ꂽ�B���̐��x�́A�C���^�[�l�b�g�Ɛڑ��\�ȃJ�����A�Z���T�ȂǗl�X��IoT���i��ΏۂƂ��āA����琻�i�ɋ������Ă���Z�L�����e�B�@�\�����ʓI�ȕ������ŕ]�����A���̌��ʂɊ�Â����x���t������������d�g�݂������̂ł���B�f�W�^�����̐i�W�ɔ����l�X��IoT���i���}���ɑ������Ă���̒��ŁAIoT���i�̍w���ҁE���B�҂��A���̐��x�̃��x�����m�F���邱�ƂŁA���炪���߂�Z�L�����e�B�����̐��i��e�ՂɑI���\�ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă���B
��̓I�ɂ́A���P�i���x��1�j���灚�S�i���x��4�j��4��ނ̃��x������߂��Ă����B���P�͋��ʂ��ċ��߂���Œ���̃Z�L�����e�B�v���A���Q�͐��i�ތ^���Ƃ̓������l���������P�ւ̒lj���{�Z�L�����e�B�v�����߂���̂ł���AIoT���i�x���_�[���炪�����i��]�������x���ւ̓K����錾����d�g�݂ł���B����ɑ��A���R�Ɓ��S�́A��O�҂����x���ւ̓K����]������d�g�݂ł���A���{�@�ւ�d�v�C���t�����ƎҁA�n�������c�́A���Ɠ��̏d�v�ȃV�X�e���ł̗��p���z�肳��Ă���B
12��16�����_�Ń��x��1�K���Ƃ���135���i���o�^����Ă���B���x��2�̐\����t��2026�N�ȍ~�̊J�n���v���Ƃ̂��Ƃł���A��O�ҕ]�����K�v�ȃ��x��3�ɂ��ẮA�ꕔ���i�ތ^���Z�L�����e�B�v���E�K����ɂ��Ẵp�u���b�N�E�R�����g��W���Ԃ��I�������ł���B
IoT�@���_���T�C�o�[�U���̋��Ђ��ۑ��ƂȂ钆�A���̐��x�͏d�v�Ȗ������ʂ������x�ƍl����B�����_�̃��x��1�ł̉^�p�܂��A���x�̍���̒����ȓW�J�����҂������B�܂��AIoT���i�x���_�[�AIoT���i���܂ރV�X�e���̐v�E�\�z���Ǝ҂��ꂼ��ɂ����Ă��̐��x�����p���������AIoT���i�P�̂����łȂ��AIoT���i���ւ��V�X�e���S�̂̃Z�L�����e�B���x���̊m�ۂɎ��g��ł����������Ƃ��]�܂��B
�y��V�ʁz 4��16���@IIJ�s���A�N�Z�X�A���{������O���[�v��n��ȂNJe���ɉe��
�`�Z�L�����e�B�ێ��ɂ͎��v�͂Ǝ��~�͂Ɓ`
IIJ�Z�L���AMX�T�[�r�X�ւ̕s���A�N�Z�X���ẮA�����ő�400�������̘R�k�\�������\���ꂽ�d��C���V�f���g�ƂȂ����B���̉e���́A���{������O���[�v�iJPX�j�╡���̒n����s�Ƃ�������Ƃɂ��g�y���A���Ƃ��܂ނ��ׂĂ̊W�҂ɏՌ��Əd�v�ȋ��P��^�����B�����Z�p�͂�����IIJ�ł��j����Ƃ��������́A�T�C�o�[�U���̍��x���ƁA�]���̃Z�L�����e�B���f���̌��E�m�Ɏ����Ă���B
���̎��Ă��������P�́AIT�T�[�r�X���Ǝ҂Ɨ��p���̑o���ɂƂ��ďd���B
�܂��A���Ǝ҂ւ̋��P�́A�u��Έ��S�_�b�̊��S�Ȃ�I���v���B�ǂ�قǖh��Z�p�𓊓����Ă��A�Ǝ㐫��ݒ�~�X�A�T�v���C�`�F�[���̂ǂ�����_��˂���郊�X�N�̓[���ł͂Ȃ��B���ꂩ��́A�u�N������邱�Ƃ�O��v�Ƃ����Z�L�����e�B�헪�ւ̓]�����s�����B�V�X�e���v�ł́A������N�����ꂽ�ۂɁu���}�Ɍ��m�ł���d�g�݁v�A���Ȃ킿�Ď��̋������ŗD�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �h��̑��d���������ĕK�v�������܂�B����ɂ͕ω����鋺�Ђɉ����Čp���I�Ȗh��̐��̌������A�������K�v�ƂȂ��Ă���B�@������a����ȏ�A�h�䎸�s���́u��Q�ɏ����v��������Ƃ̎Љ�I�ӔC�ƂȂ�B
IIJ���������Ĕ��h�~���́A���̋��P��̌����Ă���B��̓I�ɂ́A�u�T�[�r�X�ݔ��ɂ�����U�镑�����m�@�\�̋����BWeb�A�v���P�[�V�����t�@�C�A�E�H�[���̑��w���ɂ��h��̋����B�T�[�r�X�S�̂ɂ�����Ĕ��h�~��ړI�ɎВ��̒����v���W�F�N�g���B�v�Ɣ��\���ꂽ�B
���ɁA�T�[�r�X���p���ւ̋��P�ł���B���p�҂́A�x���_�[�̃u�����h��Z�p�͂��ߐM���Ă͂����Ȃ��B�T�[�r�X�I�莞�A���i��@�\�����łȂ��A�u�f�[�^���ǂ̂悤�ɕی삳��Ă��邩�v�u�C���V�f���g�Ή��̓������v����ɉ�����ׂ����B�����ĉ������A���Ȗh�q�̓O�ꂪ���߂���B�p�X���[�h�̎g��������AMFA��K�p����u���ȐӔC�����v�����߂ēO�ꂷ��K�v������B
���_�Ƃ��āA����̎����́A�Z�L�����e�B����x��������ΏI���ł͂Ȃ��A�p���I�ȉ��P�ƌ����������Ȃ��I���Ȃ��}���\���ɈႢ�Ȃ����Ƃ�F�������Ă��ꂽ�B���Ǝ҂Ɨ��p�҂����݂Ƀ��X�N��F�����A�A�g���������Ă������Ƃ��A���ꂩ��̎���ɋ��߂���B
�y��W�ʁz 4��6���@���������⒆�����Ȃǂ�ETC��Q�@7�s���A�ꕔ���[����
�`�V�X�e�����C�̕s����A�傫�ȎЉ���������炷�`
4��6�������ANEXCO�����{�Ǔ��̍������H��ETC�V�X�e����Q���������A1�s7���A17�H��106�ӏ��̗�������ETC���[�������p�ł��Ȃ��Ƃ������Ԃ������A�����܂�38���Ԃ�v�����B2km�ȏ�̏a��10�����ȏ�Ő����A�����̗��p�҂ɉe�����o���B
���ړI�Ȍ����̓V�X�e�����C�ɂ����ăf�[�^�j���������N�����Ă��܂��A�ꕔ�����ETC�J�[�h���u�ʍs�s�v�ƌ���Ĕ��肳�ꂽ���߂��B��Q�������̊����}�j���A���Ɋ�Â��ė��������ƂɌʑΉ����s���Ă������A�L���Q��z�肵������I�ȃ}�j���A�����Ȃ����ꔻ�f�������ꂽ���߁A�u�o�[�����낵���܂܈�䂸������Z�v�Ƃ����ē����������Ƃ��������̒ʉ߂��啝�ɒx��������ȗv���̂悤���B�܂��A���ɂ��Ă��e�x�Ђ̔��f�ɂ䂾�˂��Ă������߁A�ǂ��ʼn����N���Ă���̂��E�ǂ�����Ηǂ��������p�҂ɂƂ��ĕ�����Â炢���������B
IT�V�X�e���Ɋւ��҂ɂƂ��ăo�O�͂����̂ł���AETC�̂悤�Ȏ��Љ�ɑ傫���e�����y�ڂ��V�X�e���ł���V�X�e����Q���Љ�ɉe����^����Ƃ��������e�Ղɑz���ł���B����ŁA���������V�X�e�����^�p�����ƂƂ���BCP�̑z��̒��ɑ�K�̓V�X�e����Q�Ƃ������̂��z�肳��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ�����̖��̔w�i�ɂ��肻�����BOT�̈�̃f�W�^�������܂��܂��i��ł��������AIT�V�X�e���̏�Q�ɂ���Ă����ɎЉ�C���t�����~�߂Ȃ��悤�ɂ��邩�Ƃ����m�b���܂��܂����߂���悤�ɂȂ邾�낤�B���̍ۏd�v�Ȃ̂́A���Y�r�W�l�X�ɂ����āu����D�悷�邩�v����ƂƂ��Ď��m���Ă������Ƃł͂Ȃ����낤���B�Ĕ��h�~��̒��ł��u��{���j�v�Ƃ��āu��ʂ̗�����~�߂Ȃ��悤�A����ő����ɕK�v�ȑΉ����s���v�ƋL�ڂ���Ă����B���̂悤�Ȋ�{�I�ȍl���������m�O�ꂳ��Ă���A�z�肵�Ă��Ȃ���Q�����������ۂɂ�����ׂ��Ή����Ȃ����悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�Q�l�jNEXCO�����{�u�L��I��ETC�V�X�e����Q�������̊�@�Ǘ������ψ���v
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/2025_crisis-management_etc/
�y��X�ʁz 8��28���@FeliCa�̃Z�L�����e�B�Ǝ㐫�ŗ��p�҂ɕs���L����
�`�Ǝ㐫���̓`������݂̍���͐����������̂��`
2025�N8��28���A�����ʐM��FeliCa�Ɋւ���Ǝ㐫�������������ɁA�傫�ȎЉ�I�����ƕɑ��鉊�オ�������B�J�����̃\�j�[���n��FeliCa�J�[�h�s���Ă����v��Ƃ͒����ɂ��̃��X�N�ƈ��S���ɂ����R�����g�\�����B���̏��A�o�ώY�ƏȂ͌��\�O�̐Ǝ㐫�֘A���ɂ��ĊW�ғ������̐��m�ȏ�L�̏d�v���������A�ߓx�ȕs����������M�̕K�v�����������B
FeliCa�͌�ʌnIC�J�[�h��d�q�}�l�[�ȂǁA���{�̐����C���t�����x�����ՋZ�p�ł��邽�߁A�u�Ǝ㐫�v�Ƃ������t����ꂽ�i�K�ŗ��p�҂̕s�����}���Ɋg�債���B����ɉe���͈͂���Q�̗L�����\���ɐ�������Ȃ��܂ܕ����̒n���V��������ꂽ���Ƃɂ���āA���ۂɂ͉e��������I�ŁA�����ɔ�Q����������ł͂Ȃ������ɂ�������炸�A��肪�ߓx�ɑ傫�������Ă��܂����A�܂��A���{�Љ�ɂ͌����T�[�r�X�ɑ���[�����X�N���҂������A���X�N�̑��ݎ��̂����e����ɂ��������I�w�i�����̕s�����������Ă��܂����ƍl����B
�Z�L�����e�B�Ǝ㐫�̕A�ɂ����Ă͐��E�I�ɃR�[�f�B�l�[�e�b�h�E�o���i���r���e�B�E�f�B�X�N���[�W���iCVD�j���蒅���Ă���B����́A�����҂ƒ҂����O�ɒ������s���A�������������Œi�K�I�ɏ����J����d�g�݂ł���B
�č��ł�CISA�AEU�ł�ENISA�Ȃǂ���������S���A�Љ�I�e���̑傫�����ĂقǐT�d�ȏ��J�����s����B���{�ł��o�ώY�ƏȂƏ�����i�@�\�iIPA�j���Z�L�����e�B�c�̂����S�ƂȂ�Ǝ㐫���̒����E���\�ɂ��Ă��K�C�h���C������������Ă����B��������̃v���Z�X�ɑ����ĊW�҂͓����Ă����ɂ��ւ�炸���O������Ă��܂����B
����x�A���\�O�̐Ǝ㐫�֘A������舵���҂͂��̕E�J���v���Z�X�̑��݂�Ӌ`�𗝉����A�Z�p�I�Ȑ��m�������łȂ��A�u�s�����ǂ��}���邩�v�����ɂ��������J�Ɛ����ӔC���s���ł��낤�B
�y��10�ʁz 11��20���@���{���j�A2035�N�܂łɑϗʎq�v�Z�@�Í��iPQC�j�Ɉڍs
�`�ʎq�R���s���[�^�[�����p����u�n�[�x�X�g�U���v�ɔ�����`
���ƃT�C�o�[��������11��20���A���{�@�ւȂǂɂ�����ϗʎq�v�Z�@�Í��ւ̈ڍs���j�u���{�@�֓��ɂ�����ϗʎq�v�Z�@�Í��iPQC�j�ւ̈ڍs�ɂ��āi���ԂƂ�܂Ƃ߁j�v�����\�����B
����PQC�V�t�g�ƌĂԂׂ����j�́A�ʎq�R���s���[�^�[�̓o��ňÍ��̉�ǂ��e�ՂɂȂ�A�����̌��J���Í��̈��S�����ቺ���邽�߁APQC�����邱�Ƃŏd�v���������g�݂ł���B�����ł͋��Z�ƊE����N���猟�����J�n���Ă���A����͐��{���j�Ɉ���������`�ŁA���̏d�v�C���t�����Ǝ҂ɂ��g�y���A���X�̃T�v���C�`�F�[���ɓW�J���Ă������̂Ǝv����B
���Ĕ�Ȃ�b�ł��邪�A���B�ł͒E�Y�f�Љ�������т̌���ɁA2035�N�܂łɃG���W���Ԃ̐V�Ԕ̔����֎~��EV�V�t�g��ڎw���Ă������A�����̃n�C�u���b�h�Ԃ�EV�Ƃ̋����ɉ�����Ċ����~�낵���˂Ȃ��Ɋׂ��Ă���B�������AEV�V�t�g�ƈقȂ�PQC�V�t�g�̊��͊ȒP�ɍ~�낹�Ȃ��A�o�ό��ʂŕ]������Ɣ��f���ԈႦ���˂Ȃ����ł��邩�炾�B
���̗��R�̈���A���Ƃ�w�i�Ƃ����T�C�o�[�U���W�c�̑��݂ł���B�ނ�͕s���ɐގ悵���u��ǂł��Ă��Ȃ��Í������v���ʂɒ��߂��݁A�ʎq�R���s���[�^�[�̓o���҂��]��ł���B�u�n�[�x�X�g�U���v���d�|����U���҂��ʎq�R���s���[�^�[����ɂ���O�ɁA�����̈Í��Z�p��PQC�ɓ���ւ��邱�Ƃ��A���̈��S�ۏ�ɒ�������Ɛ����������D�ɗ�����B
�Ƃ͂����A���Ԋ�Ƃł̓��X�N�����݉����Ă��Ȃ��i�K�ŁA10�N��̃Z�L�����e�B��͍l���邱�Ƃ������B���̒��ŁA���Z�ƊE����s���ē������`�x�[�V�����́A�O���[�o�����Z�V�X�e�������S�Ɉێ����A���̈���ł��葱���邱�Ƃ��A�e��s�̐����c��Ɍq���邩�炩������Ȃ��B���Z�ƊE����{�Ƃ���Ȃ�A���Ԋ�Ƃɂ�����PQC�V�t�g�̈Ӗ��́A�Z�L�����e�B����������Ƃ̐����c����������R���v���C�A���X���Ɨ������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B10�N��ɏ��̂��U���҂łȂ����Ƃ��F�肽���B
�y�ԊO�ҁz 11��18���@2025�N11��18���̓C���^�[�l�b�g����ꂽ��
�`���E�I�ɘI�悵���g�f�W�^���Љ�̒P���Q�_�iSPOF�j�h���`
2025�N�́A���{�����Ɍ��炸�A���E���̃T�[�r�X����~�E�s���艻����d��ȃf�W�^���C���t����Q�����������N�������B�ے��I�ȏo�������A10��19����AWS��Q��11��18����Cloudflare��Q�ł���B��������P�ꎖ�Ǝ҂̓����g���u���ł���ɂ�������炸�A�g�y�����e���͋ɂ߂čL�͈͂ɋy�сASNS�A���ρA�s���T�[�r�X�A�I�����C���Q�[���AAI�T�[�r�X�ȂǁA���p�҂�����I�Ɉˑ����鐔�����̃f�W�^���T�[�r�X���ꎞ�I�ɋ@�\�s�S�Ɋׂ����B
���ẴC���^�[�l�b�g�́A�����K�͂̎��Ǝ҂��w�E��Ƃ����U�I�ɃT�[�r�X�����\���ŁA����ӏ��̏�Q���S�̂̒�~�ɂȂ��邱�Ƃ͔�r�I���Ȃ������B�������ߔN�́A�N���E�h��ՁACDN�A�F�T�[�r�X�A�Z�L�����e�B�Q�[�g�E�F�C�Ƃ�������Ցw���A�����̃f�W�^���C���t�����Ǝ҂֏W��Ă���B����ɂ��A���l�ȃf�W�^���T�[�r�X���g�����Ȃ��`�Łh�A����̃N���E�h��Ղ�l�b�g���[�N��ՁA�F�E�����ՁA���邢�͈ꕔ���[�W���������R���|�[�l���g�Ɉˑ�����u�W���^�\���v���`������Ă����B
10����AWS��Q�͕č������[�W�����ius-east-1�j�Ŕ����������肳�ꂽ���ɉ߂��Ȃ��������A�����̃T�[�r�X���F��f�[�^�Ǘ��̈ꕔ�����̃��[�W�����Ɉˑ����Ă������߁A���E����2000�ȏ�̊�Ƃ�T�[�r�X�ɉe�����A���{�̗��p�҂ɂ��傫�ȉe�����y�B11����Cloudflare��Q�ł����l�ɁA�ݒ�~�X��l�b�g���[�N�s����u���ɐ��E�֓`�d���AWeb�A�N�Z�X�̊�Ղ��̂��̂��h�炬�u�C���^�[�l�b�g����ꂽ�v�Ƃ��\�����ꂽ�B�����́A�f�W�^���Љ�̕\�ʂɂ͌����Ȃ��u�ˑ��W�̘A���v���A��ӏ��̏�Q��������\����I�悳��������ł���B
2025�N�̈�A�̏�Q�́A�f�W�^���Љ�ɂ����ăf�W�^���C���t���̏W�����i�ވ���A���̈ˑ��W���\���ɉ����E�F������Ă��Ȃ��������Ƃ�����ɂ��A���ʂƂ��āg�����Ȃ��W�����h���V���ȍ\���I���X�N�ƂȂ蓾�邱�Ƃ����������B
�y���m�点�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�L�����e�B�\��j���[�X�I�l�ψ���ψ����@��؞ē�Y
2001�N�Ɏn�߂܂����Z�L�����e�B�\��j���[�X�A����Ŏl�����I���߂��܂����B���̊ԓ��j���[�X�������ǂ��������܂����F�l�A�ҏW�ɎQ�����������܂����F�l�A�x���Ă����������X�^�b�t�̊F�l�ɂ��炽�߂Č��\���グ�܂��B�����g�����̃j���[�X�ɖ��N���g�ނ��Ƃő����̂��Ƃ��w���Ă��������܂����B
����25�N�̐ߖڂ������܂��ď\��j���[�X�𑲋Ƃ����Ă��������܂��B��C�͍���ψ��ɉ�����Ă��������܂������{ �ׂ���ł��B�[���Z�p�ւ̗����Ɠ��@�ŏ\��j���[�X�̓I���˂�������F���܂������t���邱�ƊԈႢ����܂���B�ǂ������������\��j���[�X�������ڂ��������܂��悤���肢�������܂��B
�F���܁A�{���ɉi���Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B
�ҏW��L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@JNSA�����ǒ��@�������m
���N���uJNSA�\��j���[�X�v���ɏo�����Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɁA��؈ψ����ƈψ��݂̂Ȃ���̂������ł��B�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
���N�̈ψ���ɂ�����ő�̃j���[�X�́A��͂��؈ψ����̑ޔC�ł��B2001�N�Ƀl�b�g���[�N���X�N�}�l�W�����g����iNRA�j�Ŏn�܂������̊����A2009�N����JNSA�Ɉ����p���A�����ɂ킽��ψ����Ƃ��Č������Ă��������܂����B���̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v���Ȃ���A�����܂ő������Ȃ������Ǝv���܂��B���N�ɂ킽�邲�s�́A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
��C�͏��{�ׂ���ł��BJNSA�̗����グ�������犈�����x���Ă�������A���݂��t�F���[�Ƃ���JNSA�̊������������Ă��������Ă��܂��B����I�l�ψ���ɉ����L�������M���Ă��������܂����B���ꂩ�����낵�����肢���܂��I
�܂��A�ψ��̌�������܂����B�{�i�ψ����ޔC����A�V�����_�R����i���������j�b�Z�C���a���Q�ی�������ЁAJNSA�C���V�f���g��Q����WG���[�_�[�j���Q�����Ă��������܂����B��������ǂ�����낵�����肢���܂��B
���N�̑I�l�ψ���̓X�P�W���[�������Ȃ�^�C�g�ł������A�ψ����̐v���ȓ������̎��M�Ɏh������A�e�ψ�����C�Ɏ��M���i�݂܂����B�������ŗ\��ʂ���J�ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B���ł���I���N���V�ψ����̂��ƁA���̐����ł��肢���܂��B�c�c�Ȃ�ď����Ă�Ɓu���O�͋C�y�ł�����ȁA����ȑʕ��ōςނ���I�v���Đ����������Ă������ł����B
�I�O�ɂȂ����j���[�X�̒��ł́A�l�I�ɃZ�L�����e�B�ƊE�̍ĕ҂��C�ɂȂ�܂����B�T�C�o�[�Z�L�����e�B�͗D�G�ȋZ�p�҂̗͂Ɉˑ��������ł����A�ŋ߂͑��͐�A�܂�p���[�Q�[���Ɉڂ����悤�Ɋ����܂��B
�����������Ă��邤���ɁA�A�X�N���Ђ̍ŐV���|�[�g���o�܂����B�F�؏��̐ގ悪�n�܂肾�Ƃ̂��ƁB�F�ؕ����Ɖ^�p�̃`�F�b�N�͋}���ł��B�Z�L�����e�B�S���݂̂Ȃ���A�撣���Ă��������I
���N�̊����́u�F�v�B���E����u�F�v�Ɓu���C�I���v�ɐU���Ă���悤�Ɍ����܂��B���N�͂����������₩�ɂȂ��Ă����������Ƃ��肢�A�ҏW��L���I���܂��B
����ł́A�悢���N�����}�����������B