JNSAメールマガジン 第77号 2016.1.8☆★☆
JNSAメールマガジン 第77号 をお届けします。
新年あけましておめでとうございます。
今年は暖冬のようでもう梅の花が咲いていてびっくりしました。
新年を迎えて落ち着いた気分でいられたのもつかの間で、みなさまも忙しい日常に戻ってしまった頃と思われます。暖冬と思っていたらまた寒くなったり体調管理も難しいですね。
今年も引き続きどうぞよろしくお願い致します。
さて、2016年初回のリレーコラムは、駒澤綜合法律事務所 弁護士である高橋郁夫様 からの寄稿をお送りします。
デジタル証拠の法律実務Q&A
(駒澤綜合法律事務所 弁護士 高橋郁夫)
昨年の9月に、私が筆頭編集者となって「デジタル証拠の法律実務Q&A」という本を日本加除出版から出版させてもらいました。この本は、私が部会長を務める第一東京弁護士会の総合法律研究所IT法部会に所属する弁護士を中心に、デジタル証拠という観点から、技術と民事・刑事の法律実務の架け橋を目指すことを目的に作成されたものです。
本日は、この「デジタル証拠の法律実務Q&A」の核をなしているデジタル証拠という考え方と、デジタル証拠が現代社会においてどのように活用されており、また、今後、どのように活用されていくのかというのを紹介することにしましょう。
私たちは、デジタルデータによって組成された証拠を「デジタル証拠」と定義し、いろいろな法的な問題を検討しました。証拠といっても、裁判所に甲1号証とかいって提出するだけではありません。企業の不正隠蔽を図る電子メールであっても証拠とかんがえることができますし、また、情報漏えいがなされた際のログのデータも、広い意味で、証拠ということができるでしょう。情報化社会の加速度的な発展によって企業や個人の活動に伴う各種情報がデジタルデータの形で膨大に生成・流通、蓄積されるようになったことは、社会のすべての側面を変えているということができます。法律実務の世界は、事実にもとづいて人の社会的な権利・義務・利益を決定するというものですから、このことで非常に強く影響を受けているのは、当然だといえます。
デジタル証拠という考え方は、情報セキュリティの分野とも非常に親しい関係にあるということができます。この本では、1990年代前半のスティーブ・ジャクソンゲームズ事件や90年代後半のハイテク犯罪対応をめぐる議論などを歴史とともに紹介しています。また、わが国におけるベッコアメ事件(95年)や越後湯沢のハイテク犯罪対応ワークシップ(97年)を懐かしく思い出す人もいるかもしれません。また、2000年代にはいると、デジタル・フォレンジックスは、その後、重要な分野として技術と法の両面からの分析がなされるのにいたりましたし、ライブドア送金メール騒動事件(‘06年)、検察官による証拠改ざん問題(‘10年)、PC遠隔操作事件(‘12年)などは、新聞の社会面を賑わす問題となりました。これらの事件の基礎的な知識は、情報セキュリティの分野に関心のある人の教養として必要なものかしれません。
概念や歴史的な分析が、いわば、導入だとすれば、本書のメインは、デジタル証拠の技術的な側面に関する分析と民事・刑事の側面に関する分析となります。
デジタルデータというのがどのようなもので、記録媒体にどのように記録されるか、メタデータとは何か、ログとは何かというのは、この記事をお読みの方であれば、基礎的な知識になるのかもしれません。この本は、それらの知識をもとにデータの復元/パスワード解析の手法・プロセスやデジタル・フォレンジックスの概念についての分析をなしています。また、デジタル証拠の識別・収集・検査・報告というプロセスごとに技術的/法律的に問題になる点について検討しています。このあたりは、情報セキュリティ担当者でも、あまり詳しくはないという方がいるかもしれません。ぜひとも参考にしてください。
「デジタル証拠に証拠能力はあるのか」という疑問について、民事ならば、証拠能力は当然に認められますよ、この質問は、証拠能力と証明力の違いを意識していない法律の素人からなされた質問かもしれませんというのが、民事の実務問題の最初の解説になります。これ以降、この本は、デジタル証拠においては、何を対象として裁判官の心証が形成されるのか、とか、デジタル証拠における原本や写しとは何か、どのように提出するかという問題について議論しています。また、名誉毀損事件などにおける発信者の特定方法から検索サービス提供者に対する請求をめぐる近時の裁判例の紹介、また、コンピュータプログラムの瑕疵(不完全さ)の立証をめぐる問題など、最新のIT法の到達点を示しています。
さらに刑事事件における問題については、新しい技術をもちいた捜査手法としてどのようなものがあるか、それらが、法的にどのように位置づけられるのか、令状による捜査手法において問題はないか、デジタル証拠に対する標準的な取得・分析の過程・手法などは何かなどの論点が紹介されています。
現在、企業法務においては、不正調査、海外訴訟対応において、デジタル証拠のみならず、従来の紙の証拠をもスキャンして、それらを、キーワードなどで探索した上に、弁護士などによって分析していくドキュメントレビューという手続がきわめて重要な役割をしめるようになってきています。事案に関連する証拠を、お互いに開示をしあって、あたかもトランプの絵柄を表にしてポーカーをするようにして正義が実現されるという考え方が、世界的に一般化しつつあり、不正調査、海外訴訟対応においては、そのような理念に基づいた対応が求められるようになってきています。会計不正などで、不正の文化を示すようなキーワードが見つかったという新聞報道は、そのような手続によって調査がなされたことを示唆しているといえるでしょうデジタル証拠によって変貌しつつある法務の姿と将来をテーマに分析している記述になります。
法律家の世界は、いまだに紙・ファクシミリでなんとかやっている世界であり、また、法律家自体にも、情報通信技術は、にが手な人が多い印象なのですが、それでも、たくさんの弁護士が執筆に参加しました。その上、実際に法律の本としてランキングにはいったのです。このことは、保守的で、情報化社会を拒みつつあるかのような法律の世界にも、新たな風が吹き始めたことを示しているのかもしれません。
#連載リレーコラム、ここまで
<お断り>本稿の内容は著者の個人的見解であり、所属企業及びその業務と関係するものではありません。
【部会・WG便り】
★JNSA未来予測プロジェクトメンバーによる発行書籍『サイバーセキュリティ2020 脅威の近未来予測』が1月末の発行予定で、一般書店で発売されることになりました。2月初めには大手書店を中心に本屋店頭で買えるようになりますので、ぜひお手にとってご覧下さい!
https://www.jnsa.org/result/2015/miraiyosoku.html
【事務局からの連絡、お知らせ】
★今年度のJNSA表彰受賞者を発表しました。
https://www.jnsa.org/jnsaaward/2015/winner.html
★JNSAセキュリティ十大ニュースを発行しました。ぜひご覧下さい。
https://www.jnsa.org/active/news10/
★JNSAも構成団体となっております新生「辻井重男セキュリティ論文賞」の応募期限は1月12日(火)です。ぜひ興味ある方は振るってご応募下さい。
http://www.jssm.net/wp/?p=1702
☆コラムに関するご意見、お問い合わせ等はJNSA事務局までお願いします。
*************************************
JNSAメールマガジン 第77号
発信日:2016年1月12日
発行: JNSA事務局
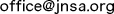
*************************************