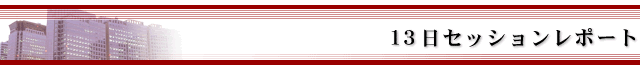加藤氏の講演ではVirusについて、最新のVirus事情からVirusのアクション研究、感染方法の変化、感染と被害拡大の原因、そして、これからのVirus対策という順序で、ご説明があった。
講演の中で,最近のVirusの特徴としてトロイの木馬型とスクリプト型が増えておりNimda、Sircam、Badtransなど、InternetExplorerなどの脆弱性を利用して、ホームページやメールを媒介として増殖するVirusが増加傾向にあるという認識を示されていた。
中でも特に、スクリプト型は、中の構造がスクリプトである(構文自体が読める)ため、コンピュータ技術者ではなくても本を見ながら比較的簡単に亜種を作れてしまうことが被害を増加させているというご説明があった。また、トロイの木馬型は、あるソフト固有のセキュリティホールを利用して動作するVirusであり、そのソフトを使用していなければ問題はないが、OutlookExpressなど使用人数の多いソフトウェアでは被害が爆発的に増加してしまう。
また、最近ではW杯があることから「KoreaJapanResult」というような件名で送られ、W杯速報のように見せかけて感染させるようなウィルスも登場している。その対策として、パッチを適用するということがあるけれども、日々増えつづけるVirusに対しIEのセキュリティパッチ(5MBから10MB)を日々確認し、毎回適用しつづけるのは大変でなかなか最新の状態を保つことが出来ないのではないか、という問題点も挙げられていた。現在、CableTVやADSLなどの常時接続を利用している人数も増えてきてはいるものの、まだアナログ回線で通信している人も少なくなく、OSや各種パッチなどはあまりアナログ回線の利用者のことを考えていない、という指摘もされていた。
これからのVirus対策として、定義ファイルや検索エンジンのバージョン、サービスパックやパッチの情報、使用しているソフトウェアのバージョン、IPアドレスとOSの種類等といった情報をしっかりと管理しておくことが重要になるだろう。この点については,システム部門の担当者が管理するというのはやはり一人では50台が限界で、それ以上の場合には、利用者各自がしっかりと管理するべきである、という認識を示しておられた。また、利用者個々人の負担を減らすため、ウィルス対処(スキャン)個所の分散化を実現する,ルータのようなゲート型での対策が必要とされるということや、ネットワーク内に未登録のコンピュータがないかなどの把握が必要であるという点についても言及しておられた。
このような講演を拝聴して、筆者としては,ふたつの点に強く印象付けられた。
まず一点目は、スクリプト型のウィルスに関する点である。講演の中では,夏休みなどになると、学生が改造した亜種などが出回るために被害が増加するというご説明であった。専門知識を必要とせずに、悪意もなくただ面白半分でウィルスがばら撒かれるという状況に対して、コンピュータの利用者一個人として、しっかりと自分の身は自分で守らなければならないということを再認識させられた。
二点目は、ウィルス対策ソフトは日夜定義ファイルが更新されており、最新版を入れておかなければウィルスに対して安全とはいえないということである。どちらも自分が被害にあわず、また加害者にならぬようにするためには必要なことであるということを再認識した。
講演を拝聴して、ウィルスに対して、「自分はあのソフトを入れているから心配ない」というような油断が命取りとなるということを、改めて認識した次第である。
株式会社ラック セキュアネットサービス事業本部プロジェクト推進部
阿部 正道